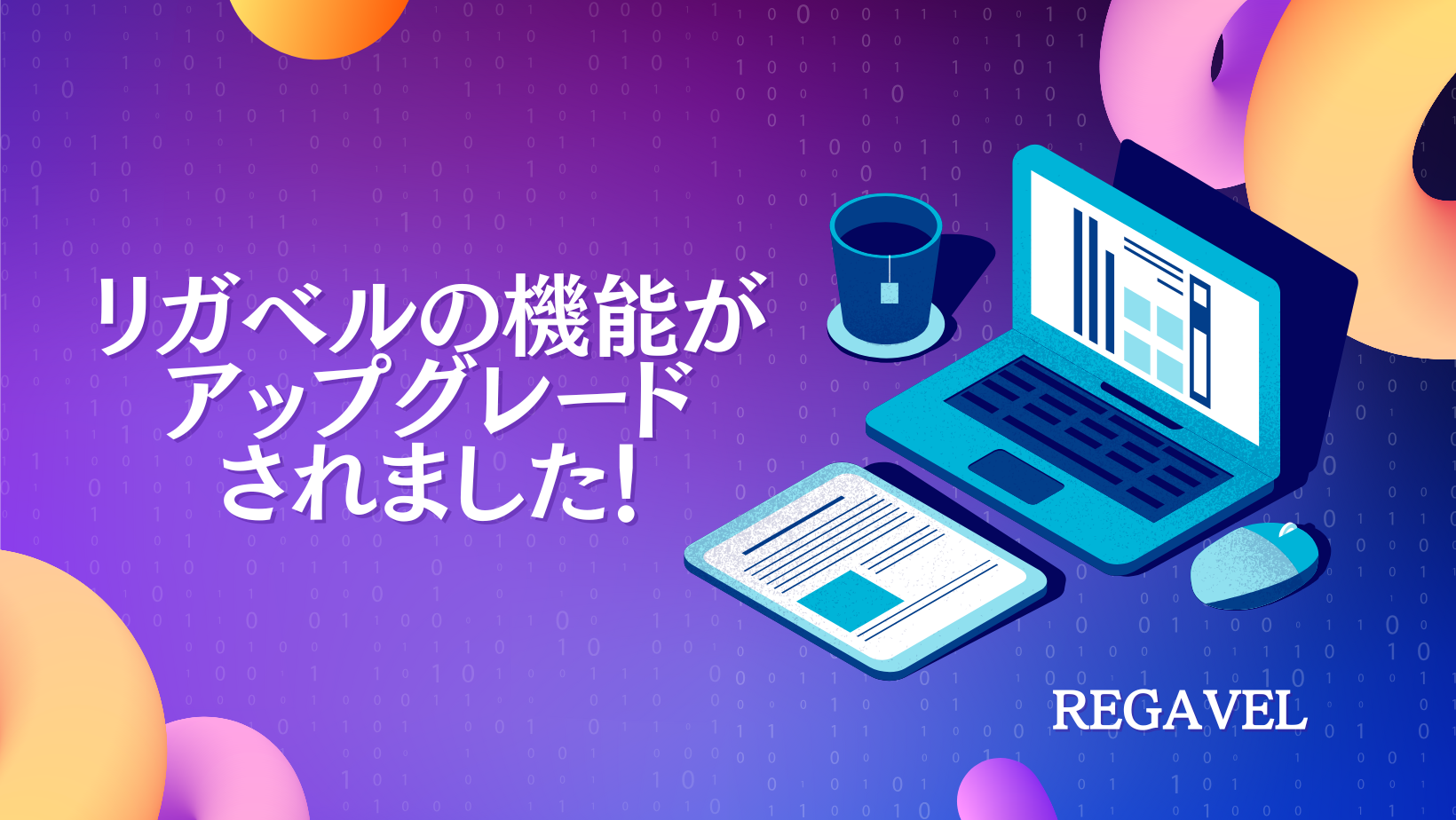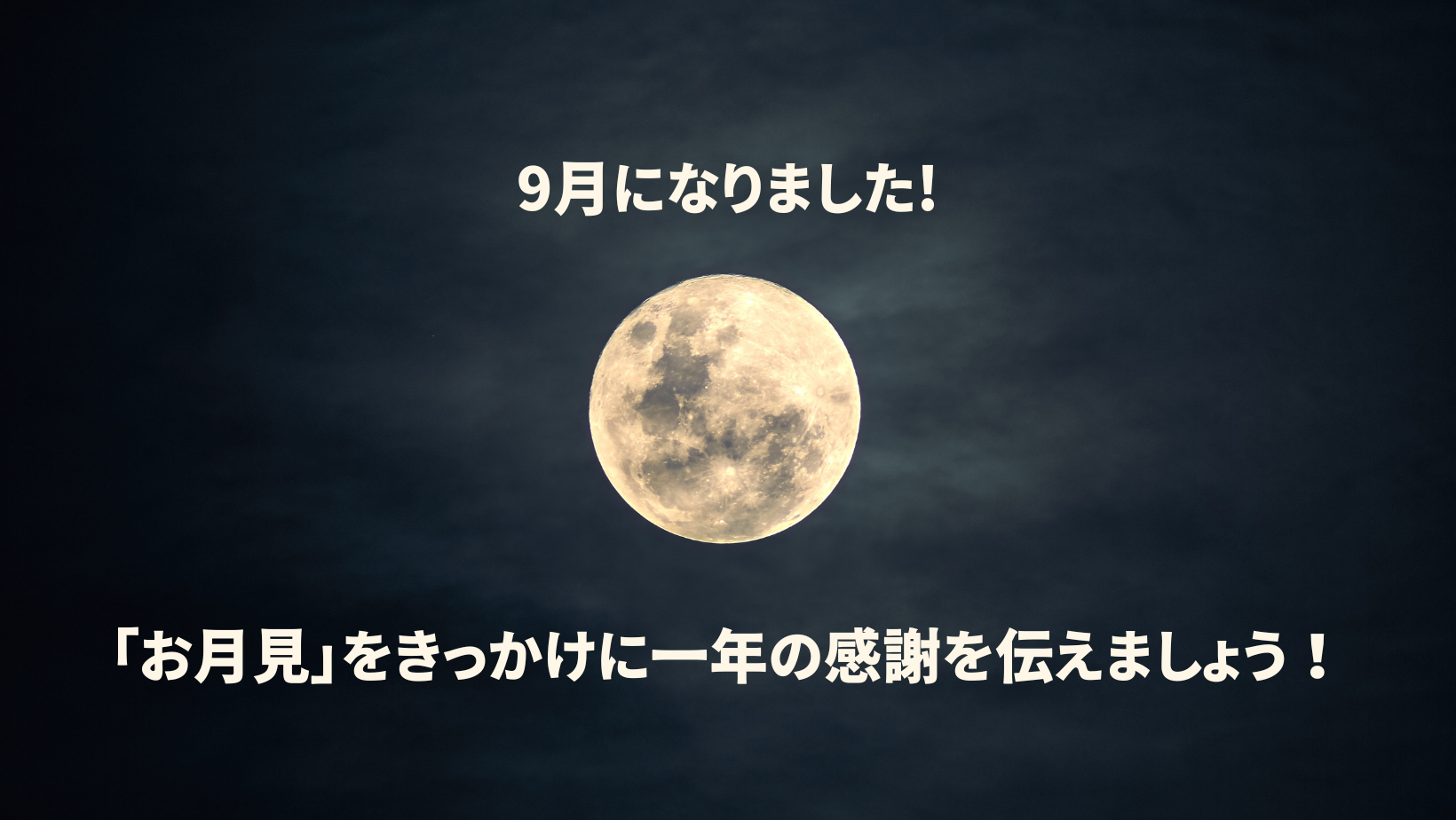個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方とは?
コラム | 不動産知識
2024/02/05

個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方を知っていますか?
身内や友人に不動産を売却するんだけど、契約書類ってどうした方がいいのと思っている方もいらっしゃると思います。
そんな方向けに個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。
個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
合わせて個人間で不動産売買する時の基礎知識も紹介します。
この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。
| この記事の監修者 |
|
田中利貴文 |
|
 |
|
宅地建物取引士、一級建物アドバイザー、住宅ローンアドバイザー。 大工として7年間現場を経験し、その後現場監督として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。入社より2年で、トップセールスを達成。 2012年8月に独立し不動産売買仲介を主にした株式会社レンズを創業。創業から11年目にして売り上げは、毎年右肩上がり。独自の住宅ブランド「インフィーア」は、独自性があり性能が高いと好評。 趣味は、ツーリングで自然を見に行くのと、筋トレ、読書。 |
|
|
|
|
個人間で不動産売買する時の基礎知識

不動産の売買は個人間でも行える
不動産の取引では、良い買主を見つける事が難しい場合があります。
しかし、知人や友人の中に「不動産を購入したい」という人がおり、売主も「売却しても良い」と考えていれば、取引する事ができます。
具体的には、自分の土地を隣の方に譲渡する、土地を貸している人に売る、自身の土地に建物を所有していても、底地部分を売却するなどがあります。
最近では、インターネット上でも個人間の不動産取引サイトが登場し、人気があります。
不動産売買を個人間でする行うメリット2つ
・仲介手数料が必要ない
不動産の個人間売買の最大のメリットは、仲介手数料が必要ないというところです。
通常の不動産取引では、法定の仲介手数料がかかり、例えば3,000万円のマンションの場合、売主は96万円(3%+ 6万円)の仲介手数料と消費税を支払わなければなりません。
しかし、個人間売買では不動産会社が介在しないため、仲介手数料の支払いやそれに伴う消費税の負担が発生しません。
・友人や知人と取引をするので安心
不動産取引は、高額のため、売主と買主に精神的な負担がかかります。
個人間売買では、親族や長い付き合いのある友人などが買主となることが一般的であり、取引相手が知っている人物であるため、初対面の取引相手と比べて精神的な負担は軽減される傾向があります。
友人同士などの場合は価格交渉が発生する可能性もありますが、お互いの理解と信頼があれば大きな負担にはなりません。
不動産売買を個人間でする行うデメリット4つ
・融資を受けられない可能性がある
個人間売買のデメリットとして、融資が難しくなる可能性が挙げられます。
理由は、重要事項説明書がないなどです。
通常、不動産会社を介した取引では、購入する不動産についての詳細を説明するための重要事項説明書が作成されます。
重要事項説明書は、トラブル回避のために、不動産の状態や重要な事項が記載されています。
しかし、個人間売買では重要事項説明書の提供が必須ではないため、金融機関が融資の判断材料が足りず、融資が難しくなります。
・お互いに負担が大きい
不動産の売買は、売主と買主の双方にとって重要な取引となるため、手続きを細心の注意を払って進める必要があります。
特に、個人間売買では不動産会社が介入しないため、契約書類、価格交渉、所有権移転の登記手続きなど、全ての手続きを売主と買主が自ら行わなければなりません。
これらの作業にはリスクが潜んでおり、手続き上の不備が大きなトラブルとなる可能性もあります。
そのため、売主と買主の負担は相当に大きくなると言えます。
・書類の作成が難しい
個人間売買契約は通常、売主が「売ります」と意思表示し、買主が「買います」という意思表示で成立します。
民法上でも規定されていますが、実際の不動産取引契約書の作成は専門家であっても難しいことがあります。
事務手続きや法的な取り決めなどの確認が必要であり、不動産の売買契約書を法的に有効なものとするためには慎重な対応が求められます。
個人間売買においては、重要事項説明書の交付が義務付けられていませんが、これに近い内容が売買契約書に含まれることが一般的です。
個人で売買契約書を作成する場合は、将来のトラブル回避のためにも法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する事をおすすめします。
・瑕疵担保責任を負う必要がある
契約不適合責任は、不具合を知った時から1年以内に買主から通知を受け、5年以内に権利を行使された場合には、契約不適合責任を負う必要があります。
しかし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や、重大な過失によって見過ごしていた場合は、この期限は適用されません。
また売主が個人の場合は、契約不適合責任を免責することもできます。
不動産業者(宅建業者)が売主の場合は、宅建業法によると引渡しから最低2年以上契約不適合責任を負う必要があります。
不動産業者間の取引では、契約不適合責任を免責できますが、売主が不動産業者で、買主が個人の場合は免責はできません。
瑕疵担保責任は、購入した不動産に欠陥がある場合、売主が補償し、場合によっては契約解除も可能というものです。
例えば、シロアリの被害、排水管の設備の不具合、雨漏りなどが認められた場合は、売主が責任を負う必要があります。
買主が知り合いであっても、これらの問題を確実に解消しないと、将来的なトラブルの原因となる可能性があるため、慎重に対処しましょう。
個人間で不動産売買をする時に必要な契約書
不動産売買契約書
売買代金固定型と売買代金清算型の契約は、通常土地建物と土地の取引において行われる契約形態です。
売買代金固定型では、契約時に使用される面積が、登記簿の面積か契約時の実測図で確定され、この数値を元にして取引が行われます。
一方、売買代金清算型では、登記簿や実測図に基づいて契約時の売買価格を算出し、最終的な取引時に再度実測図を測定して得られた広さに基づいて最終的な売買価格が決定されます。
特に土地の場合、登記面積と実測面積が異なることがあるため、これらの契約形態が利用されることがあります。
区分所有建物の契約書
区分所有建物は、通常マンションの事です。
古いマンションの場合、登記簿において土地と建物が分かれて記載されることがあります。
しかし、平成以降のマンションでは、権利形態が土地と建物を一体化した形態となり、これを総称して敷地権と呼びます。
マンションの敷地権については、建物の登記簿だけで確認できます。
具体的には、敷地権の種類(所有権や地上権など)が記載され、これらの権利に基づいて各戸の土地の所有割合が記載されています。
借地権付き建物売買契約書
借地権は、建物の所有者が、その建物を保有するために土地を借りる権利の事です。
物権の一種である地上権や賃借権としての借地権が存在します。
地上権は土地を借りて建物を所有する権利で、賃借権としての借地権は土地を借りて建物を権利として所有する権利です。
通常、借地権の価値は所有権の70〜80%程度と言われており、このため借地権者は土地の所有者である底地権を取得することが一般的です。
これにより、土地の所有権を持つことで建物の安定的な保有が可能になります。
個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方
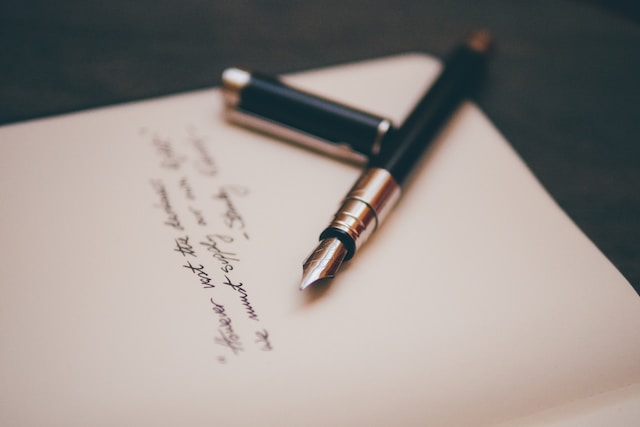
契約書に必ず記載しなければならない13項目
・売買物件の表示
物件の情報は、売買契約書において重要な要素であり、通常登記記録に基づいて記載されます。
物件情報には土地や建物の詳細な情報が含まれ、これが契約の基本となります。
取り扱う物件の情報に誤りがあると、将来的にトラブルの原因となる可能性があるため、非常に慎重な確認が必要です。
契約書に表示された情報が登記記録と一致しているかを確認し、正確であることを確認することが重要です。
・売買代金、手付金の額、支払期日
売主と買主は事前に交渉し合った売買代金の記載と手付金の金額とその支払い期日の記載をする必要があります。
手付金は、買主が売主に対して支払う保証金であり、通常売買代金に含まれます。
一般的には売買代金の5〜10%が手付金として設定されますが、この金額については両者の合意が必要です。
手付金の支払い日や最終的な売買代金の支払期日も契約上の重要事項です。
買主は期日を守り、遅れがないようにする必要があります。
・土地の実測及び土地代金の精算
不動産の登記記録には、土地の面積が書かれていますが、売主はこの記録と実際の面積が一致しているか確認する必要があります。
登記記録の面積と実測された面積に誤差がある場合、その誤差分を土地代金として精算することがあるため、確認しましょう。
誤差が発生した場合、それに伴う金額の取り決めや調整を行うことで、双方が公平な形で取引を進めることが可能です。
このようなトラブルを避けるために、事前に確認作業を怠らず、正確な情報を得るように心がけましょう。
・所有権の移転と引き渡しの時期
不動産の取引では、一般的に支払いが完了した日に物件の受け渡しと所有権移転登記に必要な書類などが引き渡されます。
そのため、契約前に引っ越しの予定や互いの事情について事前に確認し、所有権の移転や引き渡しの時期を合意しておくことが重要です。
これらの詳細を契約書に記載することで、取引当日やその前後に発生するトラブルを防ぎ、円滑な引き渡しや登記手続きを確実に進めることができます。
相手方とのコミュニケーションを大切にし、明確なスケジュールを共有することがスムーズな不動産取引につながります。
・付帯設備等の引継ぎ
個人売買では主に中古住宅が売却されることが一般的です。
この際、物件自体だけでなく、内部の設備や敷地内の植物など、引き渡す対象を明確に提示することが重要です。
引き渡しと撤去の対象を明確に選別せずにおくと、トラブルの原因になることがあります。
売主と買主はしっかりと話し合い、物件に関する付帯設備の引き渡しについて共通の認識を持つように心がけましょう。
契約書などで明示的に取り決めを行い、細かな部分まで合意を確認することが、円滑な取引とトラブルを回避するための対策になります。
・負担の消除
負担の消除では、売主が買主に対して完全な所有権を引き渡すことが可能かどうかを確認する必要があります。
例えば、抵当権や賃借権など、買主の所有権を制限する原因がある場合、これらを確実に無くす必要があります。
契約を結ぶ前に、物件に関する権利や担保に関する事項を確認し、それらが買主の完全な所有権を妨げないようにすることが大切です。
これにより、取引後にトラブルを避け、円滑な引き渡しと所有権移転を実現することができます。
・公租公課等の精算
不動産の引き渡し時には、一部の税金の精算が必要となります。
固定資産税や都市計画税などです。
これらの税金は通常、1月1日時点で不動産を所有している人に対して1年分が課税されるため、年の途中で売買が行われる場合、負担の割合を話し合う必要があります。
一般的には、引き渡しを行った日を境にして所有している日数で割合を決めることが多いですが、具体的な割り当てについては契約書や合意書でしっかりと決めると良いです。
・手付解除の期限
契約を解除しなければならない場合、手付金の解除がいつまで有効かは重要です。解約手付金の有効期間については、当事者間の合意によって決めることができます。具体的な解約手付の条件や期間は契約書に明示されることが一般的です。
契約を解除できないようにするための条件や手付金解除が可能な期間を設定することもあります。
これらの事項は、売主と買主が丁寧に話し合って取り決め、契約書に適切に記載することが重要です。
・契約違反による解除
契約に違反した場合、違反した側が違約金を支払い契約を解除するというものです。
違約金の設定は契約書に記載され、通常は売買代金のおおよそ20%までの範囲で設定されることが一般的です。
このような取り決めは、契約の履行を促進する一方で、違反行為があった場合に備えて公平な補償が期待できます。
契約書では、具体的な違反事項、違約金の発生条件、金額について詳しく決めると良いです。
双方が契約書の取り決めに従い、適切な対応ができるようにすることが重要です。
・引渡し前の物件の滅失・毀損
契約成立後に自然災害などで物件が滅失または毀損した場合、通常の契約では売主、買主のどちらも責任を負わないとされることが多いです。
このような状況に備えて、契約締結前に滅失、毀損に対する取り決めを契約書に記載することが重要です。
契約書において、物件が不測の事態で損傷を受けた場合の責任分担、解決策、保険適用の有無などについて合意しておくことをおすすめします。
双方が納得する取り決めを行うことで、災害や損傷が発生した場合でも円滑に対処できます。
・反社会勢力の排除条項
平成23年6月以降に導入された反社会勢力排除条項では、不動産取引において相手方が反社会的勢力との関わりがある場合に契約を解除できるようにするための内容です。
具体的な事項として、売主及び買主が、暴力団等反社会的勢力ではないこと、物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点にしないことなどが挙げられます。
これらの内容は契約書に記載され、双方が確認した上で契約を進めることが重要です。
不測の事態に備え、契約時に反社会勢力排除条項が含まれていることを確認し、関わりを排除するための措置を共有することが不動産取引において重要です。
・ローン特約
買主がローンを組んで物件の購入を検討する場合、通常はローン特約が行われます。
この特約には、買主がローン審査に通過しなかった場合に買主が無条件で売買契約を解除できる旨が記載されています。
これにより、買主がローン審査に通過しなかった場合でも、契約は解除可能となります。
この特約において、買主は、信頼性が求められます。
売主は買主がローンを得られるかどうかを信頼し、契約を結ぶことになります。
互いに情報を提供し、円滑な取引が行えるように協力する必要があります。
・契約不適合責任
契約不適合責任は、引き渡し後に確認していなかった欠陥が発覚した場合、売主が負うべき責任です。
契約不適合責任については、契約書で具体的な規定を行う必要があります。
これには、売主がどれくらいの期間内で契約不適合責任を負うか、責任を負う範囲や条件などが含まれます。
契約不適合責任の期間の長さは、売主と買主のリスクを左右します。
責任を負う期間が長ければ長いほど、売主のリスクが高まり、逆に短ければ買主のリスクが高まります。
契約不適合責任に関するトラブルを避けるためには、契約書に明確で公平な条件を盛り込む必要があり、両者が合意し納得した上で契約内容を確認することが重要です。
個人間で不動産売買をする時の契約書を作る時の注意点

契約内容をしっかりと確認する
契約書は法的拘束力を持つ非常に重要な書類であり、一度締結した契約は簡単に破棄できません。
契約内容を確認せずに作成すると、認識の相違や将来的な大きなトラブルの原因になりかねません。
契約を結ぶ際には、細かい点も含めて契約内容を理解し、納得した上で進めることが重要です。
分からない点がある場合は、理解するまで契約を進めないよう心がけましょう。
この段階での丁寧な確認が損失やトラブルを防ぐコツです。
・契約不適合責任について知る
契約書に含まれる契約不適合責任は、物件を引き渡した後に隠れた不備があった場合に売主が負う責任です。
この内容は、互いにしっかりと理解し合意する必要があります。
契約不適合責任に関するトラブルは、個人売買で最もよく発生するトラブルの一つです。
民法では、引き渡しから10年後までに隠れた欠陥が発見された場合、売主が責任を負うことが規定されています。
ただし、宅建業法では、特約として契約不適合責任の通知期間を「物件を引渡した日から2年」と設定することも可能です。
契約書には売主がどれくらいの期間まで契約不適合責任を負うかを具体的に定めることが一般的です。
例えば、引き渡しの〇か月後までなどです。
売主がこの知識を把握し、契約時に明確に確認する必要があります。
適切な契約条件を設けることで、将来的な損害を回避し、トラブルを防ぐことができます。
自分で作成するのが難しい場合は司法書士に依頼するのがおすすめ

司法書士への相談は、個人間売買の契約書作成する際におすすめの方法です。
司法書士は、法律的なアドバイスや不動産登記のプロとして契約書の作成もサポートしてくれ、トラブルを未然に防ぐ助けになります。
しかし相談には、費用がかかるため、事前に費用について確認しておくことが重要です。
司法書士に作成を依頼するメリット
司法書士に依頼するメリットは、正確で安心できるサポートが期待できることです。
司法書士は国家資格を持つ専門家であり、不動産取引において的確なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。
特に不動産売買は重要な取引であり、司法書士の知識と経験で、抜け漏れや間違いのリスクを最小限に抑えられます。
不動産取引において安心感と効率性を求めるなら、司法書士への相談がおすすめです。
司法書士に作成を依頼する時の費用操作
司法書士に依頼する料金は、事務所によって異なり、完全自由化されています。
以前は「司法書士報酬規定」に基づいていましたが、現在は、各事務所が独自に料金を決定しています。
また、サポートの内容によっても料金が変動するため、事前に確認をしましょう。
例えば、ある事務所では権利証整理サービスとして、不動産の調査や書類作成などが含まれたパックを提供しており、依頼することで料金を抑えることも可能です。依頼する際には、複数の事務所の料金やサービスを比較して検討すると良いでしょう。
まとめ
今回は、個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方などについて詳しく紹介しました。
個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
契約書に必ず記載しなければならない13項目があります。
自分で作成するのが難しい場合は司法書士に相談してみましょう。
紹介した内容を参考にして個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方に関する知識を深めて下さい。
この記事の関連記事

2025年現在の東京の不動産市況:売り時はいつか?
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…

[再建築不可] 接道義務と43条但し書きとは
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…

[不動産査定] 不動産の路線価とは何なのか?計算方法をご紹介
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…

埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良い?
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…

横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社は?
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…

不動産売却の費用を詳しく解説
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…

不動産売買契約書とは?
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…

不動産相続手続きとは?
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…