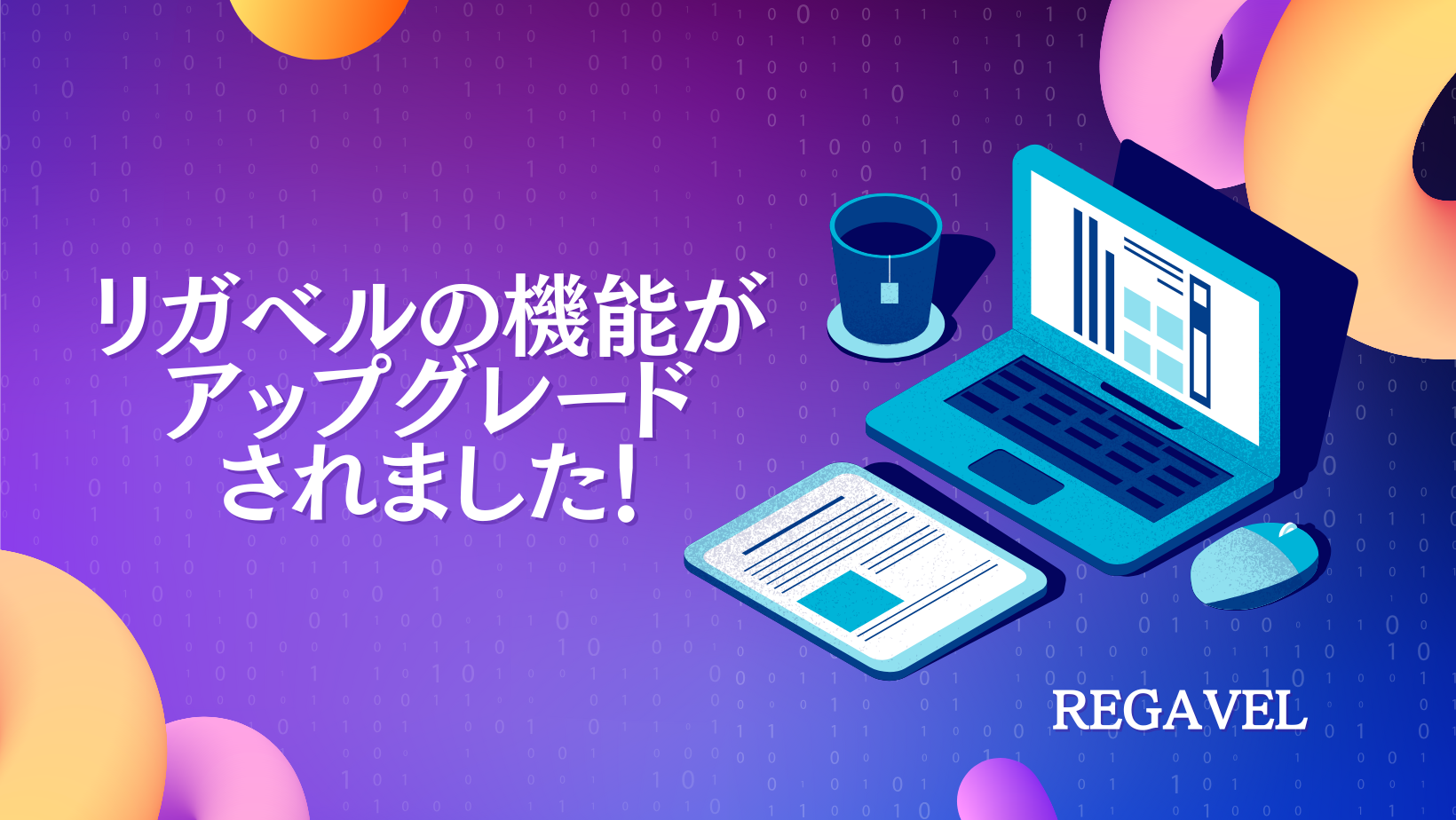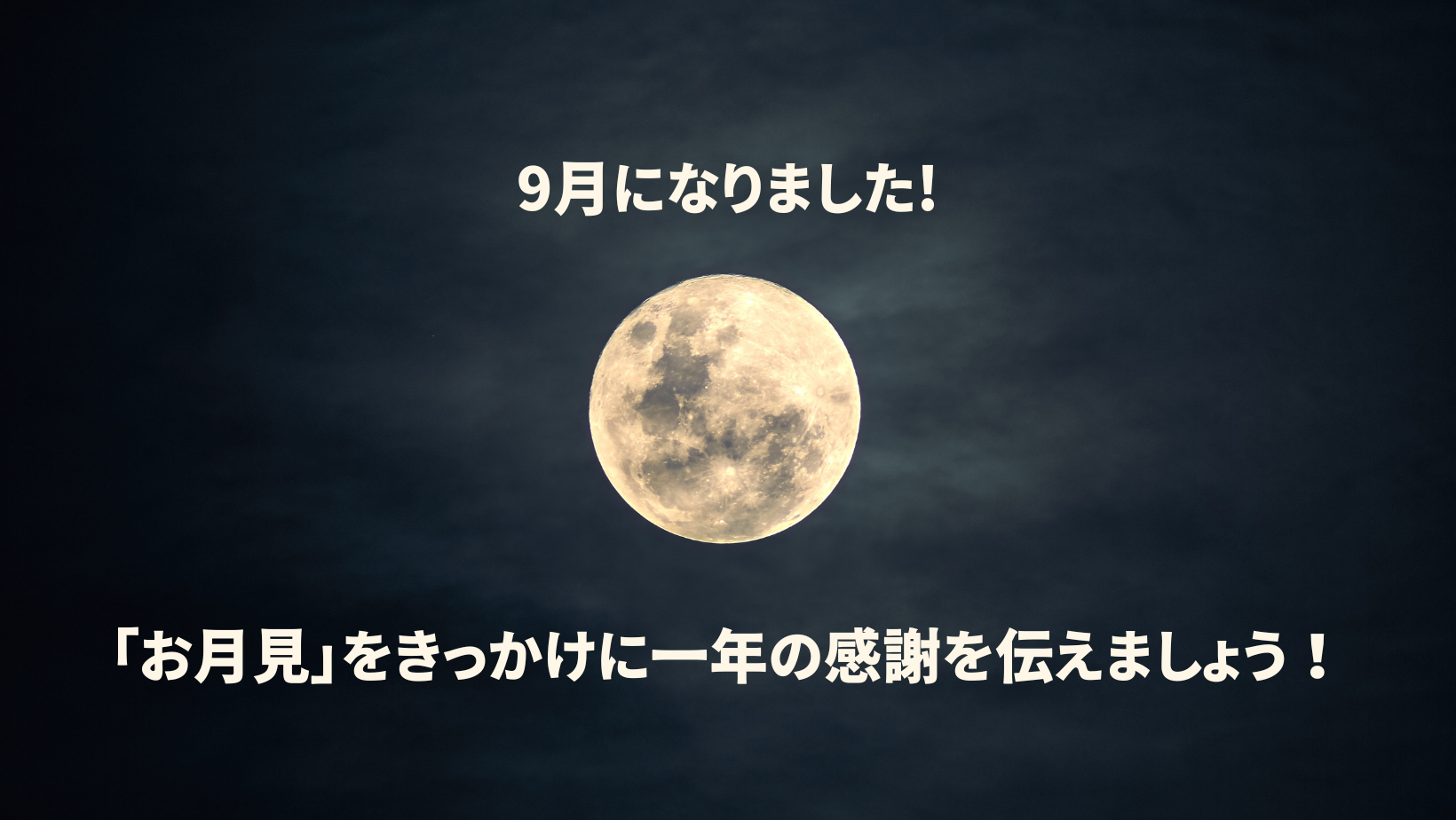不動産相続手続きとは?
コラム | 不動産知識
2024/08/20

不動産相続手続きを知っていますか?
不動産を相続することになったけど手続きについてわからなくて不安になっている方もいらっしゃると思います。
そんな方向けに不動産相続手続きについて解説したいと思いますので読んでみて下さい。
不動産相続手続きについてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
この記事では以下の内容について解説していきます。
----------------------------------------------------------------
・不動産相続手続きの流れ
・不動産を相続する方法
・不動産を相続する時の評価方法
・相続登記とは?
・司法書士に不動産相続の手続きを依頼するメリット
----------------------------------------------------------------
この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。
| この記事の監修者 |
|
田中利貴文 |
|
 |
|
宅地建物取引士、一級建物アドバイザー、住宅ローンアドバイザー。 大工として7年間現場を経験し、その後現場監督として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。入社より2年で、トップセールスを達成。 2012年8月に独立し不動産売買仲介を主にした株式会社レンズを創業。創業から11年目にして売り上げは、毎年右肩上がり。独自の住宅ブランド「インフィーア」は、独自性があり性能が高いと好評。 趣味は、ツーリングで自然を見に行くのと、筋トレ、読書。 |
|
|
|
|
不動産相続手続きの流れ

◼︎ 遺言書の確認
相続が始まったら、まず遺言書を探します。
遺言書が存在すれば、その内容に基づいて相続が進行します。
遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合でも、遺言書の内容が優先されます。
◼︎ 相続人の特定
遺言書の有無を確認しつつ、早期に相続人を特定します。
相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調査します。
新たな相続人が後から見つかった場合、遺産分割協議を再度行う必要があります。
◼︎ 財産の特定と財産目録の作成
相続人を特定する作業と並行して、被相続人の財産を特定し、財産目録を作成します。
不動産が相続財産に含まれているかどうかは、市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書で確認します。
さらに、課税明細書を発行した市区町村の役所で「名寄帳」の写しを取得すると、その市区町村で被相続人が所有する不動産の情報を一覧で確認できます。
◼︎ 遺産分割協議の実施
遺言書がある場合は、その内容に従って相続が進行します。
遺言書がない場合は、全ての相続人で遺産分割協議を行います。
協議で分割内容に合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、誰がどのように財産を相続するかを記載します。
◼︎ 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
不動産を相続する際には、相続登記を行い、被相続人から相続人への名義変更を行います。相続登記には、登記事項証明書などの書類が必要ですので、事前に準備しておきます。
◼︎ 相続税の申告と納付
相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内が相続税の申告、納付期限です。
期限内に申告、納付しないと、相続税に関する特例が適用されない可能性がありますし、無申告加算税や延滞税が課せられることもありますので、注意が必要です。
不動産を相続する方法

◼︎ 現物分割による直接的な相続
現物分割とは、財産(不動産を含む)をそのままの形で相続する方法を指します。
例えば、2つの不動産を2人の相続人が現物分割で相続する場合、それぞれが1つの不動産を相続します。
この方法は、不動産を売却して現金化する方法と比べて手続きが簡易ですが、評価額が異なる不動産を分割する際には、評価額の低い不動産を相続した人が不公平を感じる可能性があります。
◼︎ 代償分割による相続と補償
代償分割は、一部の相続人が現物で財産を相続し、その他の相続人に対して補償を行う方法です。例えば、被相続人の子ども2人が相続人で、相続財産が評価額5,000万円の不動産のみである場合、1人が不動産を相続し、もう1人に対して2,500万円の補償を行うことになります。
ただし、当事者間で合意があれば、補償の額は必ずしも均等である必要はありません。
◼︎ 換価分割による売却と分配
換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。
例えば、不動産の売却価格が3,000万円で、相続人が3人である場合、それぞれが1,000万円ずつ相続します。
換価分割は、相続人が不動産の相続を望まない場合や、相続税の支払い資金が不足している場合などに利用されます。
◼︎ 共有名義による複数人での所有
不動産の相続方法として、複数の相続人が共有名義で相続するという手法もあります。
共有名義にする場合、各相続人が所有する割合を持分として設定し、それを登記します。
ただし、不動産を複数の相続人が共有名義で相続すると、以下のような問題が生じる可能性があるため、共有名義とする際には十分な検討が必要です。
・一人の相続人が単独でその家に住む場合、他の相続人は退去を求めることができない。
・不動産を売却する場合、全ての共有者の同意が必要となる。
・固定資産税の支払いについて、支払わない者がいると、他の相続人に連帯納付義務が発生する。
・共有者の一人が相続すると、その相続人の配偶者や子どもが新たな共有者となり、トラブルが発生しやすくなる。
不動産を相続する時の評価方法

不動産を相続する際、その評価額を把握することが必要となります。
相続税申告における不動産の評価は、購入価格や建築費ではなく、時価に基づいて行われます。
しかし、土地の時価を正確に把握することは困難であるため、相続税の申告を容易にし、課税の公平性を確保するために、国税局は毎年、全国の民有地の評価額の基準となる路線価と評価倍率を公開しています。
不動産の評価基準は、土地であれば路線価、家屋であれば固定資産税評価額となります。
また、居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)については、令和5年10月6日に国税庁から「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が発表され、令和6年1月1日以降に相続・遺贈・贈与(以下、相続等)によって取得した居住用区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の相続税評価が変更されました。
◼︎ 土地の評価方法
土地の評価額は、基本的には路線価を基準とした路線価方式で評価しますが、路線価が設定されていない地域では倍率方式で評価します。
・路線価方式
路線価は、土地が面する道路ごとに設定された土地の価格で、国税庁の路線価図・評価倍率表で確認できます。この路線価を基準に評価額を算出する方法を路線価方式と呼びます。
路線価は、1平方メートルあたりの価格が千円単位で表記されており、「200A」と記載されていれば、1平方メートルあたりの価格は20万円です。
これに、面積や道路からの奥行きによって価格を補正する奥行価格補正率などを掛けることで、その土地の評価額を計算することができます。
なお、建物の所有を目的に土地を借りる権利である借地権の評価額は、その土地の評価額に借地権割合を掛けて算出します。
借地権割合は、路線価の数字の後ろにあるアルファベットで表されており、借地権割合90%のAから借地権割合30%のGまで、10%刻みで設定されています。
・倍率方式
倍率方式は、路線価が設定されていない土地の評価額を算出する方法です。
固定資産税評価額を基準に、その土地に設定された倍率を掛けて評価額を算出します。
倍率も、国税庁の路線価図・評価倍率表で確認できます。
◼︎ 家屋の評価方法
家屋の評価は、固定資産税評価額がそのまま相続時の不動産評価額となります。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる課税明細書に記載されていますが、手元に課税明細書がない場合は市区町村役場の窓口で確認できます。
◼︎ 居住用の区分所有財産の評価方法
居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)の価額は以下のように算出します。
居住用の区分所有財産 = 区分所有権の価額+ 敷地利用権の価額
区分所有権の価額 = 従来の 区分所有権の価額× 区分所有補正率
家屋の固定資産税評価額 × 1.0
・区分所有補正率
以下の4つの指標からマンションの市場価格と相続税評価額の乖離度合いを基に計算したもの
①築年数
②総階数
③所在階
④敷地持分狭小度
一室の建物床面積に対し、マンション全体の土地のうち区分所有者に帰属する面積の狭さ
敷地利用権の価額 = 従来の敷地利用権の価額 × 区分所有補正率
相続登記とは?

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が死亡した際に、その所有権を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。
不動産の所有者は、法務局によって管理される登記簿に記載されています。
しかし、所有者が死亡した場合でも、法務局が自動的に名義を変更することはありません。したがって、所有者が死亡した場合、その不動産を相続した人は、「相続を原因とする所有権移転登記」、つまり相続登記を行う必要があります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、不動産を相続した人が申請人となり、申請を行います。
◼︎ 相続登記に必要な費用
・相続登記の必要書類の取得費用(数千円〜)
相続登記を行うためには、市(区)役所で発行される証明書が必要で、それぞれに発行手数料が必要です。
必要な証明書とその手数料は以下の通りです。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
改製原戸籍謄本:1通750円
戸籍の附票の写し:1通300円
(除)住民票の写し:1通200~300円(自治体により異なる)
印鑑証明書:1通200~300円(自治体により異なる)
固定資産評価証明書:1通200~400円(自治体により異なる)
これらの証明書は1通あたりの手数料は大きな金額ではありませんが、相続登記に必要な証明書は1通では足りません。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本も含む)、法定相続人については現在の戸籍謄本が必要となります。
必要な戸籍謄本の通数は相続関係により異なりますが、配偶者や子が法定相続人になるシンプルな相続の場合でも、5〜10通程度必要になることが多いです。
亡くなった人が転籍(本籍地を変更すること)を繰り返していた場合や、兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、さらに通数が増えます。
また、「代襲相続」(相続人が被相続人より前に死亡し、その子が相続人になる場合)や「数次相続」(相続登記をしないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生する場合)では、必要な戸籍が数十通になることもあります。
2024年3月からは、最寄りの市(区)役所で、必要な戸籍謄本をまとめて取得できるようになりました。
本籍地が遠方にあっても、最寄りの窓口で請求が可能です。
本人だけでなく、配偶者、父母・祖父母、子・孫の戸籍謄本も請求できます。
ただし、兄弟姉妹の戸籍謄本や、コンピューター化されていない戸籍謄本は請求できないため、それぞれ本籍地のある市(区)役所を訪れるか、郵送で請求する必要があります。
マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が可能な市町村もありますが、自治体によって対応は異なりますので、詳細は各自治体に確認してください。
・相続登記の登録免許税
⚪︎固定資産税評価額が1000万円の場合、4万円が必要
登録免許税は、登記申請時に国庫に納付する税金です。
税額は、土地や建物の固定資産税評価額に対して法定税率を適用して計算されます。
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の算定基準となる土地や建物の価格を指します。
これは毎年自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
相続による所有権移転登記の税率は1000分の4と定められています。
したがって、計算式は次のようになります。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%(4/1,000)
例えば、固定資産税評価額が1000万円の土地の場合、登録免許税として4万円を納付する必要があります。
⚪︎法定相続人以外への遺贈には、登録免許税の税率が高くなる
特に注意が必要なのは、登記原因が「遺贈」の場合です。
「遺贈」は、遺言により財産を無償で譲渡することを指し、受遺者(財産を譲られる人)には特別な制限がないため、法定相続人以外の人にも財産を継承させることが可能です。
法定相続人以外の人が遺贈により不動産を取得する場合、税率は1000分の4ではなく、1000分の20となります。
1000万円の土地の登録免許税は20万円となります。
したがって、法定相続人以外の人が取得者となる場合は、税率に注意が必要です。
⚪️登録免許税が非課税となる場合もある
原則として、登記申請時には登録免許税を納付する必要がありますが、相続登記を推進するための登録免許税の免税措置が設けられています。
これは令和7年3月31日までの期間限定で、以下のいずれかに該当する場合、登録免許税は非課税となります。
・相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡した場合
・評価額が100万円以下の土地について相続登記を行う場合
・表題部所有者のみが登記された評価額100万円以下の土地について、相続人名義で所有権
保存登記を行う場合
・司法書士の報酬と費用について
相続登記を自分で行う場合、主な費用は登録免許税と必要書類の取得費用です。
しかし、司法書士に登記申請を依頼する場合、その報酬も考慮に入れる必要があります。
⚪️報酬の目安
平成30年に日本司法書士会連合会が行ったアンケート結果によれば、相続登記の司法書士報酬の目安は5〜15万円程度です。
ただし、地域や個々の司法書士により、最低額と最高額に差があります。
⚪︎報酬の加算
司法書士の報酬は自由化されており、各司法書士が自由に設定できます。
そのため、具体的な報酬については、依頼する司法書士に直接問い合わせる必要があります。
一般的には、基本報酬に加えて、相続人の数や不動産の個数に応じて報酬が加算されます。
⚪︎別途報酬
戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼する場合、これらのサービスに対して別途報酬が発生することがあります。
司法書士に不動産相続の手続きを依頼するメリット

◼︎ 相続登記のエキスパートプロなので安心できる
司法書士は、登記手続きのプロフェッショナルです。
相続登記では、登記申請書の作成だけでなく、事前の相続人調査や法務局への申請手続きも含めて、全てを司法書士に委託することが可能です。
相続登記の前には、相続人の特定のための調査が必要ですが、多数の戸籍謄本を取得する必要があるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。
特に、おじ・おばの相続や二次相続が発生しているような複雑なケースでは、初めから司法書士に任せることで安心できます。
また、その他の必要書類の取得や法務局への提出も依頼できます。
◼︎ 遺産分割協議も扱える
司法書士には、相続登記の申請書に添付する遺産分割協議書の作成も依頼できます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を文書化したものです。
故人が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決定する必要があります。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には厳格な形式はありません。
しかし、不動産の表示を正確に記述し、法的に有効な内容を適切に記載する必要があり、慎重な作成が求められます。
遺産分割協議書に不備があると、相続登記が受け付けられません。
遺産分割協議書の作成は、専門家である司法書士に依頼することで安心できます。
◼︎ 遺言書の検認も可能
被相続人が自筆証書遺言を残している場合、検認の手続きが必要となります。
検認とは、家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を保全する手続きのことです。
検認を受けていない遺言書は、相続手続きに使用することはできません。
また、相続人等が遺言書の検認を怠ると、5万円以下の過料が科せられる民法の規定も存在します。
司法書士は自筆証書遺言の検認手続きも扱うことができます。
検認を申し立てる際には、戸籍謄本を集め、それと一緒に検認申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。
司法書士には戸籍謄本の収集と検認申立書の作成を依頼できますので、司法書士に依頼することで、迅速に検認手続きを完了し、相続手続きに取り組むことが可能になります。
◼︎ 認知症の人、行方不明者、未成年者が相続人であっても対応可能
相続人の中に認知症の人、行方不明者、未成年者などがいる場合、本人が遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議の前に、家庭裁判所で代理人を選任する手続き等が必要となります。
認知症の人については、成年後見人を任命する必要があります。
成年後見人が選任されていない場合、法定後見制度を利用し、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任する必要があります。
行方不明者については、不在者財産管理人を選任するか、あるいは失踪宣告を申し立てる必要があります。
どちらの場合も、家庭裁判所での手続きが必要です。
未成年者については、通常は親権者が代理人となります。
しかし、親権者も相続人となっている場合、利益相反となるため親権者が代理人となることはできません。
このような場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成できるため、これらの申立て手続きをサポートしてもらえます。
相続を司法書士に相談すれば、成年後見人、不在者財産管理人、特別代理人の選任等が必要な場合でも一括して対応してもらえ、スムーズに相続手続きが完了します。
◼︎ 相続放棄の申述も可能
親族が亡くなり相続人になったが、相続したくないというケースもあります。
特に、被相続人が借金を残している場合、相続すると借金も引き継がれます。
また、被相続人との交流がなかったため、相続に関与したくないというケースもあります。このような場合、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行うと、相続人ではないとして扱われます。
司法書士は相続放棄の申述も扱うことができます。
3ヶ月の期間を延長したい場合、期間延長の手続きも行ってもらえます。
被相続人に借金があることを知らずに3ヶ月の期間が過ぎてしまった場合でも、司法書士に依頼して事情説明書を作成してもらえます。
◼︎ 相続手続きの報酬がリーズナブル
司法書士の相続手続きの報酬は、他の専門家と比べてかなりリーズナブルです。
弁護士は主に紛争の解決を担当しますので、弁護士に相続を依頼すると報酬が高くなります。行政書士は手頃なイメージがありますが、相続手続きの報酬は司法書士と同等です。
司法書士は相続登記まで一貫して対応してくれるので、司法書士に依頼する方がお得です。
相続について相談したい場合、市役所などで無料相談がありますが、専門家に相談する必要がないと感じるかもしれません。
しかし、司法書士に直接相談する場合でも、初回はほとんどの場合、相談料は無料です。
相続に関する相談は、最初から司法書士にすることをおすすめします。
まとめ
今回は、不動産相続手続きについて詳しく解説しました。
不動産相続手続きについて知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
紹介した内容を参考にして不動産相続手続きに関する知識を深めて下さい。
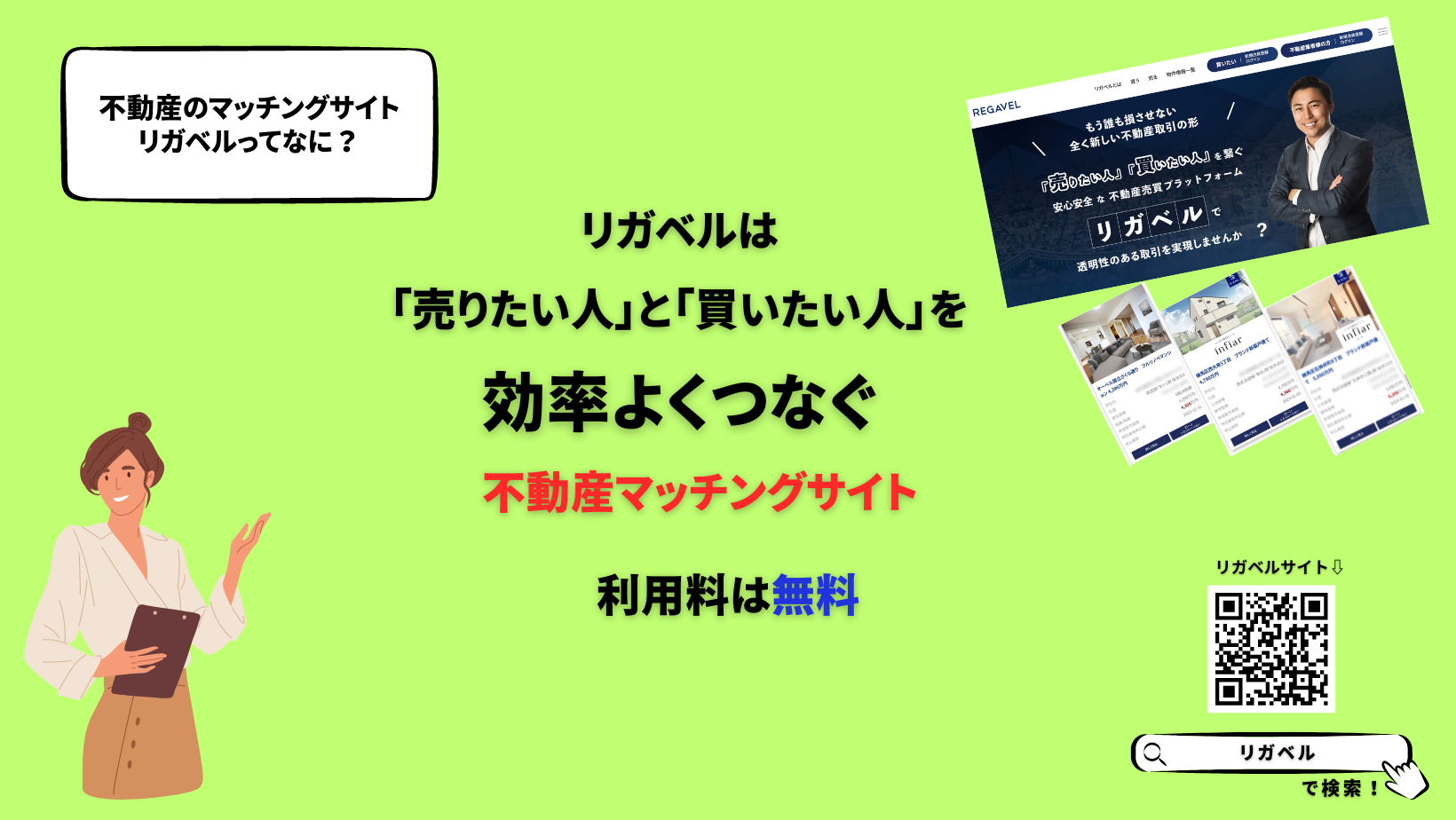
不動産取引に透明性を持たせて安心した取引ができることを目指したのがリガベルです。
リガベルは、不動産オークション風のマッチングサイトです。
買い手と売り手を繋ぐ不動産マッチングサービス!
ニッチなところに手が届くサービス。
利用料は無料です。お気軽にお試しいただけます!
リガベル公式サイト:
https://regavel-auction.com
LINE登録をしていただいた方に特典として、「売却のすべて」がわかる資料をお配りしています✨
⇩
QRコード、もしくはリンクよりお友達登録?✨
LINE:
不動産知識コラム:
https://regavel-auction.com/info/column/
ご利用ガイド:
https://regavel-auction.com/guide/
インスタ:
https://www.instagram.com/regavel_official/
その他の、不動産相続関連の記事は以下もぜひご覧ください。
不動産相続手続きとは?
https://regavel-auction.com/info/647/
相続した不動産の評価額の調べ方とは?
https://regavel-auction.com/info/639
相続した不動産を売却した時の税金とは?
https://regavel-auction.com/info/640/
その他の、不動産売買に関しての以下の記事も併せてご覧ください。
不動産売買契約書とは?
https://regavel-auction.com/info/646/
不動産売却の費用を詳しく解説
https://regavel-auction.com/info/644/
【不動産売買必要書類】売主が準備する書類とは?
https://regavel-auction.com/info/637/
不動産の売買の流れとは?
https://regavel-auction.com/info/636/
不動産を早く売る売却方法とは?
https://regavel-auction.com/info/633/
その他の、確定申告に関しての記事は以下もぜひご覧ください。
不動産売却をした時に確定申告は不要?確定申告に必要な書類も紹介
https://regavel-auction.com/info/620/
不動産売却の確定申告必要書類とは?
https://regavel-auction.com/info/616/
この記事の関連記事

2025年現在の東京の不動産市況:売り時はいつか?
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…

[再建築不可] 接道義務と43条但し書きとは
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…

[不動産査定] 不動産の路線価とは何なのか?計算方法をご紹介
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…

埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良い?
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…

横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社は?
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…

不動産売却の費用を詳しく解説
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…

不動産売買契約書とは?
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…

不動産相続手続きとは?
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…