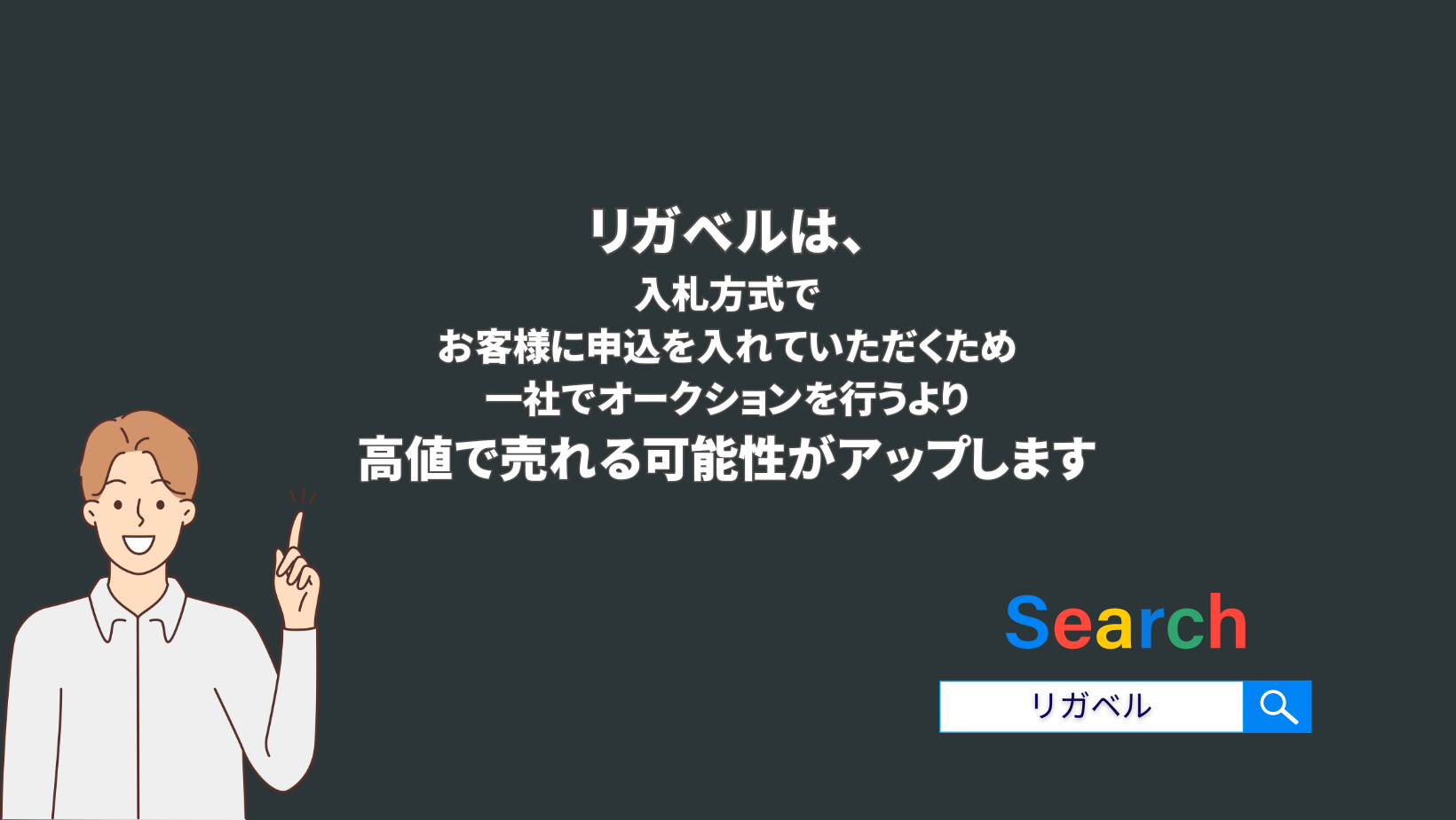不動産相続税金対策とは?
コラム | 不動産知識
2024/02/08

不動産相続税金対策などを知っていますか?
相続って複雑でよくわからない。なるべく税金控除の仕組みを利用したいけど、多すぎてわからないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
そんな方向けに不動産相続税金対策について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。
不動産相続税金対策についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
合わせて不動産相続の流れなど基礎的な事も紹介しますので参考にしてみて下さい。
この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。
| この記事の監修者 |
|
田中利貴文 |
|
 |
|
宅地建物取引士、一級建物アドバイザー、住宅ローンアドバイザー。 大工として7年間現場を経験し、その後現場監督として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。入社より2年で、トップセールスを達成。 2012年8月に独立し不動産売買仲介を主にした株式会社レンズを創業。創業から11年目にして売り上げは、毎年右肩上がり。独自の住宅ブランド「インフィーア」は、独自性があり性能が高いと好評。 趣味は、ツーリングで自然を見に行くのと、筋トレ、読書。 |
|
|
|
|
その他の、不動産相続関連の記事は以下もぜひご覧ください。
不動産相続税金対策とは?
https://regavel-auction.com/info/609/
相続不動産売却手順とは?
https://regavel-auction.com/info/613/
不動産相続登記に必要な書類は?
https://regavel-auction.com/info/614/
不動産相続の名義変更必要書類とは?
https://regavel-auction.com/info/615/
その他の、不動産売買に関しての以下の記事も併せてご覧ください。
不動産売買の仲介手数料の費用相場とは?
https://regavel-auction.com/info/604/
不動産売買の消費税の基礎知識を紹介
https://regavel-auction.com/info/618/
個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方とは?
https://regavel-auction.com/info/603/
不動産売買事例を調べる方法とは?売却相場を調べる方法も紹介
https://regavel-auction.com/info/619/
相続対策とは

相続対策とは、財産の円滑な移転を確実にするための戦略です。
財産の分配を円滑に進め、相続税の負担を軽減することがその目的です。
将来の事態に備え、遺産を有利に扱うためには、相続税対策が必要です。
相続税を節税する
相続税対策とは、相続税を最小限に抑える方法です。
相続財産の正味総額が基礎控除額を超えると、超過分が相続税の対象となります。生前に相続財産を減らす対策や相続税の支払いに備えた資金の用意は、円滑な財産移動を促進する重要な手段です。
不動産相続の流れ
相続が発生してから相続税の申告、納付までの流れを以下にまとめます。
1. 遺言書の確認
相続が発生したら、まず遺言書を探し、内容に基づいて相続を進めます。
遺言書がない場合は、そのまま次に進みます。
2. 相続人の確定
遺言書の有無を確認しながら、相続人をできるだけ早く確定させます。
戸籍謄本を取得して相続人を特定し、新たな相続人が後から発覚しないようにします。
3. 財産目録の作成
相続人の確定とともに、被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。
市区町村の固定資産税の課税明細書や名寄帳から不動産情報を取得します。
4. 遺産分割協議
遺言書があればその内容に基づき、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
5. 相続財産の名義変更
相続登記を行い、不動産などの相続財産の名義を変更します。
必要な書類を用意して相続登記を進めます。
6. 相続税の申告・納付
相続税の申告書を提出し、相続税を納付します。
適切な書類を揃え、手続きを行います。
不動産相続費用相場

登録免許税
登録免許税は、不動産の名義変更時に発生する税金で、相続した不動産の「固定資産税評価額」を基に計算されます。
具体的な計算方法は、固定資産税評価額✕0.4%で登録免許税額が求められ、価格に対する目安は以下の通りです。
・1000万円
4万円
・3000万円
12万円
・5000万円
20万円
個人が、令和7年3月31日までに少額(100万円以下)の土地を相続した場合には、登録免許税の免除措置も適用可能です。
国税局リンク:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
司法書士の手数料
不動産の相続手続き(相続登記)を司法書士に依頼する場合の手数料は、相続した不動産の価値や数によって変動しますが、一般的には5〜15万円前後が目安となります。
相続登記のみを依頼した場合や、戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども含めた総合的な対応を依頼した場合によって報酬支払い額が変わってきます。
相続にはこれらの費用に加えて、「相続税」がかかりますが、これは不動産を含む相続財産全体の総額に応じて課税されるため注意してください。
必要書類の取得にかかる実費
相続手続きに必要な戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの資料取得にかかる実費は、状況によって異なりますが、一般的には数千円〜1万円程度を予定しておくと良いでしょう。
生前にしておくべき相続税対策

3年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする
贈与税には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。
広く行われているのは暦年課税制度です。
暦年課税制度では、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与税はお金だけではなく、不動産・車など経済的価値のあるさまざまなものが対象となります。
110万円を超えた場合の暦年課税制度の贈与税の計算を避けるためには、非課税枠を利用して生前から時間をかけて贈与を行い、相続財産を減らすことが重要です。
贈与者の死亡日以前7年間に贈与された分は、贈与したときの時価で相続財産に加算されるルールがあります。
以前は死亡日以前3年間の贈与分でしたが、2023年度の税制改正で7年間に変更されました。
2024年1月1日以降、段階的に期間が延長され、2031年1月1日から完全に7年間の加算が適用されます。
この期間中、死亡日以前3年を超え7年以内の4年間に贈与された分については、「4年間の贈与額の合計-100万円」が加算対象額となります。そのため改正前と比較して、「4年間の贈与額の合計-100万円」の部分がプラスで計算対象になったと言えます。
「亡くなる直前に贈与した財産は相続税がかかる」というルールを考慮し、早めに対策を行うことが重要です。
相続時精算課税制度で贈与する
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子・孫へ生前贈与する贈与する時に利用できる制度のことです。
生前贈与の際に合計2,500万円までであれば何度でも贈与財産価額から控除され、贈与者が亡くなった時、相続財産に贈与で受け渡した財産を加算し、相続税を算出します。
相続時精算課税制度で受け渡した財産は、贈与時の時価で相続財産に加算されます。そのため、将来的な値上がりが見込まれる不動産や株式などの資産は、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与することがおすすめです。
値上がりした場合、その差額分だけ相続税を抑えられます。
2024年1月1日以降の改正で、年間110万円の基礎控除も設けられました。
この基礎控除は贈与税と相続税の両方に適用され、年間110万円まで非課税で、申告が不要です。
「相続時精算課税制度」は「暦年贈与」と併用することができません。一度でも相続時精算課税制度を利用すると非課税枠が適用されません。
どちらが節税になるか計算して利用することをおすすめします。
贈与税のかからない特例で贈与する
多額のお金を一度に子や孫に贈与すると、贈与税がかかりますが、特例制度を利用することで一定額まで非課税で贈与できます。
・教育資金贈与の非課税措置(上限1500万円)
・結婚・子育て資金贈与の非課税措置(上限1000万円)
これらの特例は暦年贈与と併用でき、併用することで相続財産をさらに減らす効果が期待できます。
それぞれの特例には適用期限があります。
教育資金は2026年3月末、結婚・子育て資金は2025年3月末までです。
特例を使った贈与には、もらったお金を特定の目的に使わないと課税される可能性があるため、注意が必要です。
特例を使って贈与する場合は、生活費や教育費など既存の贈与税がかからない用途ではなく、将来の教育資金や結婚、子育て資金に使われることが望ましいです。
教育に要する資金1,500万円まで贈与税が非課税
30歳未満の若者や孫に対する教育のための支援として1,500万円以下の金額を渡す場合、その贈与には贈与税が課税されません。
教育資金の贈与に関する特例は元々令和3年3月31日までの期限が設けられていましたが、後に税制改正により令和5年3月31日まで延長されました。
この特例を利用する際には、贈与者と受贈者は贈与契約を結び、金融機関を介して教育資金非課税申告書を税務署に提出し、その後受贈者名義の口座に預金する必要があります。
相続税がかからない生命保険を契約する
相続人である故人が生前に支払った生命保険料によってもらう生命保険金は、相続税の対象となります。
相続人が受取人であれば、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかからない特例があります。
生命保険も「500万円×法定相続人の数」までは非課税
受取人が相続人であれば、特例の範囲内で遺産を残すことができます。
これにより、相続税の納税資金に困ることがなくなります。
非課税枠を利用するには、「保険料負担者と被保険者=被相続人」「受取人=相続人」である必要があります。
相続放棄した場合や、受取人が被相続人になっているものに関しては非課税枠は適用されません。
税控除を利用する場合には上記の点に注意する必要があります。
小規模宅地等の特例の活用で土地評価額を80%減少
小規模宅地等の特例は、相続財産に居住や賃貸などで使用されている宅地が含まれる場合に、その土地の相続財産としての評価額を最大80%減額できる制度です。
相続財産の評価額が低くなればなるほど、相続税の負担も軽減されます。
特に宅地が遺産の大部分を占める場合、この特例を利用することで相続税の額を著しく削減できるかもしれません。
この特例が適用できる土地は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等の4つのカテゴリーに分類されます。
土地の種類によって適用できる限度面積と減額割合が異なることに注意してください。
親子で同居する
自宅の不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用すれば、評価額を330㎡まで80%減らすことができます。
この特例は、以下の人たちが利用できます。
・被相続人の配偶者
・被相続人の同居の親族
・被相続人の別居の親族(条件が厳しい)
相続が発生してから、申告期間(10ヶ月)は相続した宅地を継続して利用しておく必要があります。
また、相続税が0円でも申告が必要であり、申告期限を過ぎるまで不動産の売却はできません。
現預金で建物と土地を購入する不動産転化による相続税評価額減
相続が予測される資産を現金で保有すると、その金額が税務上で評価されます。
現金を不動産に変えることで、資産価値はそれほど減少せずに相続税の評価額を低く抑えることができます。
節税の鍵は相続財産の評価額を最小限にし、相続税を軽減させることにあります。現金資産は100%の評価を受けるため、これを不動産に変換することで大きな節税効果が期待できます。
不動産を活用する
更地や空き家を収益物件として活用することは節税対策となります。
賃貸アパートやマンションは、自宅や別荘よりも相続税評価額が低くなる傾向があります。
これは、入居者がいても自由に使えない分が評価額に反映されるためです。
所有する土地に賃貸用の建物を建て、第三者に貸している場合、その土地は「貸家建付地」と呼ばれます。
この貸家建付地と貸家は、評価額を低く抑えるための手段となります。
墓地や仏具などを生前に買って相続財産を減らす
墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産には相続税がかかりません。
これらを生前に購入しておくことで、相続時の財産を減らし、相続税を抑えることができます。
ただし、祭祀財産が礼拝用ではなく、投資目的だった場合には相続税がかかる点に注意しましょう。
購入時にローンを組んでも債務控除の対象にはなりません。
民事信託(家族信託)を活用した認知症対策
相続税対策で気になるのは、被相続人が認知症になるケースです。
生前贈与や遺言は当事者の意思に基づくため、被相続人が認知症で判断能力を喪失すると、暦年贈与が難しくなります。
このリスクに備え、被相続人に法的代理人を指定する成年後見制度があります。
しかし、最近では民事信託が家族信託として広く認知され、利用が増えています。
民事信託は営利を目的とせず、家族が被相続人の財産を管理できる制度で、金銭以外の不動産も含めて取り扱えます。
遺言書や成年後見制度よりも柔軟性があり、効果的な相続対策です。
配偶者居住権を使った節税対策
配偶者居住権は、自宅不動産の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者に「引き続き自宅に住み続ける権利」を継続させながら、かつ「生活資金の相続権利」を手にしやすくする仕組みです。
例えば、相続対象に現金2,000万円と評価額が2,000万円の不動産があった場合、配偶者が不動産2,000万円を相続して、子供が現金2,000万円を相続してしまったら配偶者は生活に必要な現金を受け取れません。
そのため、配偶者居住権で、配偶者の居住の権利を確保しながら、生活に必要な現金を配偶者が確保しやすくなるというメリットがあります。
権利の行使ができる期間としては、配偶者居住権を得た配偶者が亡くなるまでの期間です。
20年以上一緒にいた配偶者に居住用不動産を贈与する
20年以上連れ添った配偶者に対して、自宅や居住用物件の購入資金を贈与する場合、2000万円まで贈与税がかかりません。
これを活用することで、生前に配偶者に一部の自宅を贈与することで相続財産を減らすことができます。
実際には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する方が節税効果が高くなる場合があり、また不動産取得税などのコストがかかることも注意が必要です。
相続税対策の注意点

期限を守る
贈与や対策の際は、期限を守ることが重要です。
特に贈与税の確定申告期限や相続申告期限には十分に注意が必要です。
目的を明確に
各対策にはそれぞれの目的があります。
例えば、特例を利用した贈与は特定の目的でのみ使えるため、目的を明確にして実行することが大切です。
評価額の把握
贈与時の評価額が相続時に影響するため、資産の評価や将来の値上がりを検討する必要があります。
税制改正の把握
税制は変更される可能性があるため、最新の税制改正を確認し、変更があればそれに対応することが大切です。
法的アドバイスの受け入れ
相続税は複雑な法的要素を含むため、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受け入れることをおすすめします。
これらのポイントを考慮しつつ、個々の事情に合わせた戦略を検討することが相続税対策の成功に繋がります。
過度な節税は否定されるリスクあり
相続税評価額が最高裁によって否定され、国税庁の主張通りの高い評価が認められたことで、建物や土地の相続税評価額は一般的な実勢価格より低くなります。
これは相続や贈与で取得した財産を評価するための基本通達に基づくものであり、建物は固定資産税評価額×1.0、土地は路線価方式または倍率方式で評価されるためです。
老後資金とのバランスを考慮
相続税対策は計画的に行うことが重要です。
相続税を試算し、実際にかかる額を把握することで、冷静に対策を検討できます。老後資金とのバランスを考慮することで、不必要な支出を避け、安心して生活できるようになります。
家族同士が揉めないよう「争族」対策もする

争族対策はとても重要です。
具体的な対策として、家族同士の円満なコミュニケーションや遺言書の作成が挙げられます。
信頼性の高い相続専門の弁護士やアドバイザーと協力することもおすすめです。
財産の公平な分割や家族の合意形成を促進するために、事前に公正な方針を定めることが争いを防ぐ一環となります。
遺言をする
遺言書を作成することで財産の分配を明確にし、相続人間の協議を簡略化できます。
平等な分配が難しい場合、付言事項や説明を通じてなぜそのような分配を希望するのかを記載することで、相続人に理解が生まれ、紛争の予防につながります。
コミュニケーションが重要な役割を果たす争族対策として遺言書の活用があります。
生前のコミュニケーションで意思を伝える
死に対するタブー感がある中で相続の話をすることは敬遠されることもありますが、実際には健全な家族関係を築くために重要な事です。
感情的な負担を軽減し、将来のトラブルを防ぐためには、元気なうちに相続についてオープンに話し合うことがおすすめです。
家族全体で理解し合い、互いの希望や考えを共有することで、円満な相続計画が立てられます。
相続財産の一覧を作成する
財産の調査は相続手続きにおいて重要な事です。
特にデジタル資産の増加により、把握が難しくなっています。
相続人が日記や郵便物を通じて財産を洗い出す際にも、見落としが生じる可能性があります。
デジタル資産や未知の現金などが後から発見される場合、手続きの再調整が必要となります。
事前に相続財産の一覧を作成し、デジタル資産も含めて伝えておくことで、手続きを円滑に進め、家族の負担を軽減できます。
生命保険に加入し、受取人を特定の子にする
生命保険金を活用して特定の相続財産の承継をスムーズに進めるアプローチはする必要があります。
分けにくい財産に対するトラブルを軽減し、不満や紛争のリスクを低減できます。生命保険金の受取人を適切に設定しましょう。
分けにくい財産を処分する
実物資産の生前処分は相続争いの防止策としておすすめです。
不動産や高級車を売却し現金に換えることで、遺産分割がしやすくなり、納税資金の準備にも役立ちます。
しかし現金評価が実物資産より高くなりがちなことを考慮し、売却に伴う相続税の可能性も注意しておくと良いでしょう。
バランスを取りながら計画的に処分することが重要です。
まとめ
今回は、不動産相続税金対策、不動産相続に関する基本的な事などについて詳しく紹介しました。
不動産相続税金対策について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
しっかりと節税してできるだけ税金が少なくなるように工夫してみる事をおすすめします。
紹介した内容を参考にして不動産相続税金対策に関する知識を深めて下さい。
その他の、不動産相続関連の記事は以下もぜひご覧ください。
不動産相続税金対策とは?
https://regavel-auction.com/info/609/
不動産相続相談先はどこ?不動産相続を相談する時の注意点も紹介
https://regavel-auction.com/info/611/
相続不動産売却手順とは?
https://regavel-auction.com/info/613/
不動産相続登記に必要な書類は?
https://regavel-auction.com/info/614/
不動産相続の名義変更必要書類とは?
https://regavel-auction.com/info/615/
この記事の関連記事

不動産オークションサイトとは?
不動産オークションサイトを知っていますか? 不動産の…
不動産オークションサイトを知っていますか? 不動産の…

不動産の売買の流れとは?
不動産の売買の流れを知っていますか? 不動産について…
不動産の売買の流れを知っていますか? 不動産について…

不動産の個人売買サイト6選!個人売買のメリットも紹介
不動産の個人売買サイトを知っていますか? 不動産の個…
不動産の個人売買サイトを知っていますか? 不動産の個…

不動産を早く売る売却方法とは?
不動産を早く売る売却方法を知っていますか? 相続した…
不動産を早く売る売却方法を知っていますか? 相続した…
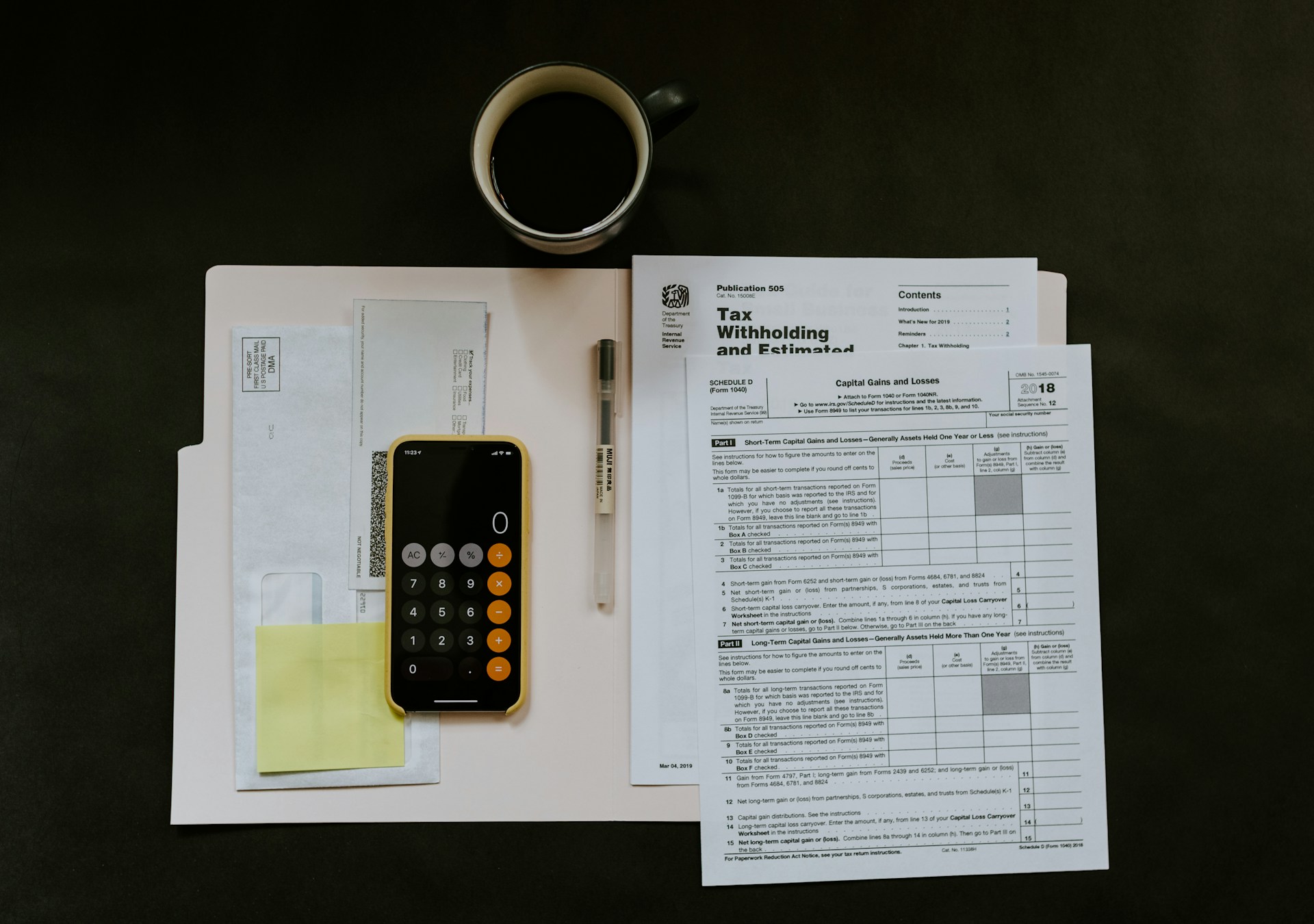
不動産売却の税金の計算方法とは?節税するコツも紹介
不動産売却の税金の計算方法などを知っていますか? …
不動産売却の税金の計算方法などを知っていますか? …

不動産売却をした時に確定申告は不要?確定申告に必要な書類も紹介
不動産売却した時に確定申告は不要なのかなどを知っていますか?…
不動産売却した時に確定申告は不要なのかなどを知っていますか?…

不動産売買事例を調べる方法とは?売却相場を調べる方法も紹介
不動産売買事例を調べる方法などを知っていますか? 不…
不動産売買事例を調べる方法などを知っていますか? 不…

不動産売買の消費税の基礎知識を紹介
不動産売買の消費税について知っていますか? 不動産売…
不動産売買の消費税について知っていますか? 不動産売…