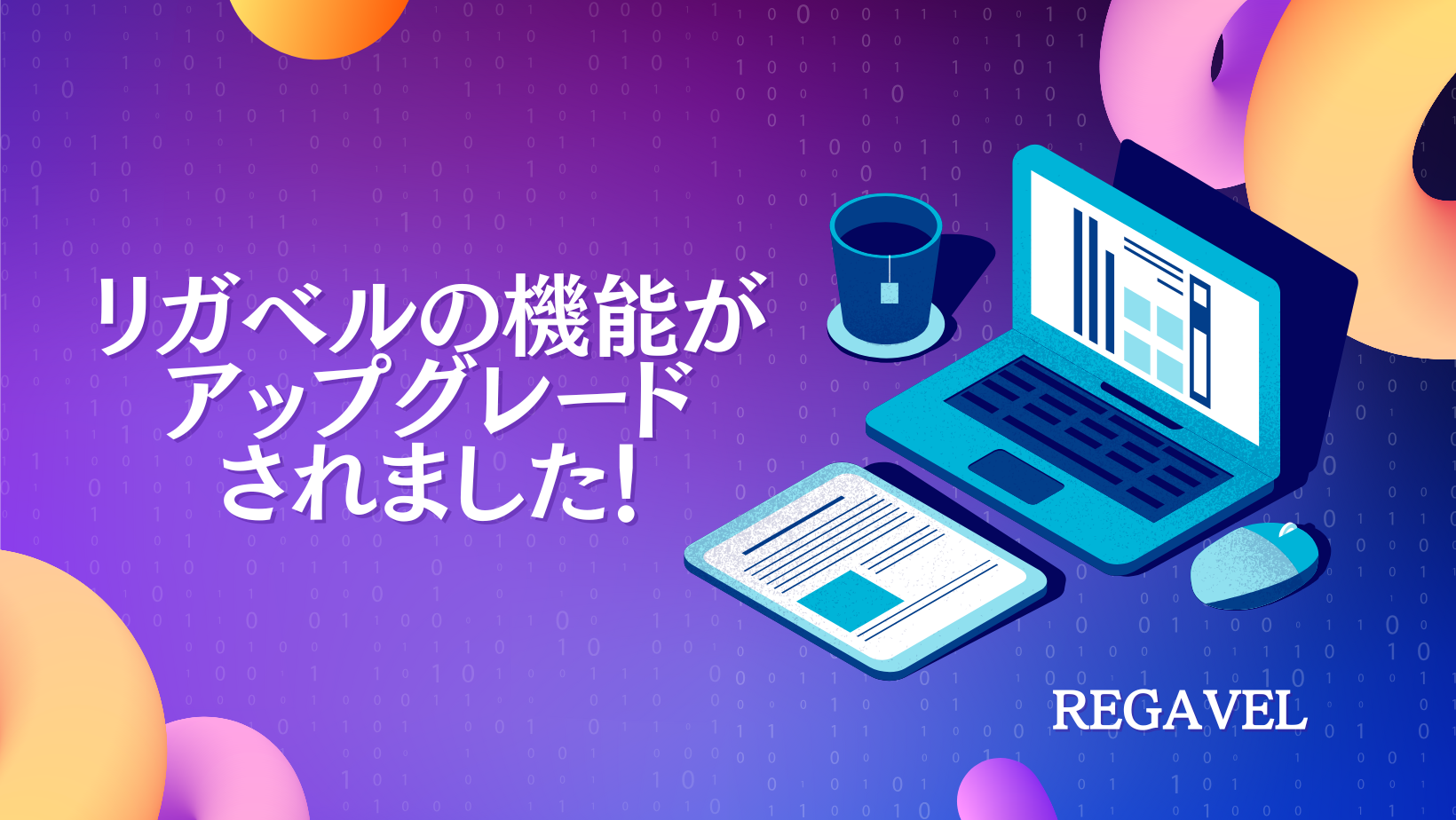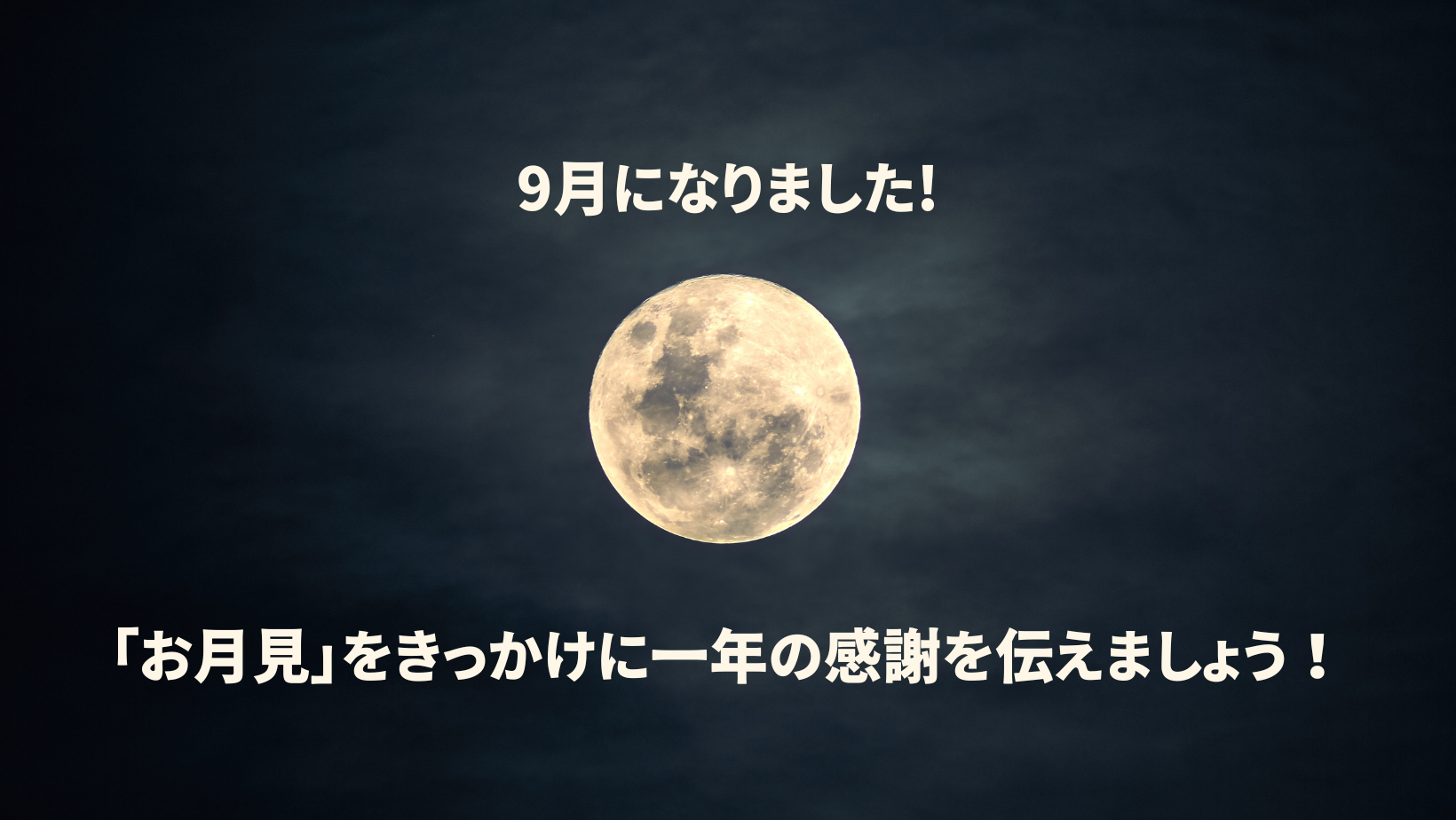相続不動産売却手順とは?
コラム | 不動産知識
2024/02/13

相続不動産売却手順などを知っていますか?
不動産を相続することになったけど、何から手をつけたらいいのかわからないと思っている方もいらっしゃると思います。
そんな方向けに相続不動産売却手順について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。
相続不動産売却手順についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
合わせて、相続登記の申請の流れと費用も紹介しますので参考にしてみて下さい。
この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。
| この記事の監修者 |
|
田中利貴文 |
|
 |
|
宅地建物取引士、一級建物アドバイザー、住宅ローンアドバイザー。 大工として7年間現場を経験し、その後現場監督として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。入社より2年で、トップセールスを達成。 2012年8月に独立し不動産売買仲介を主にした株式会社レンズを創業。創業から11年目にして売り上げは、毎年右肩上がり。独自の住宅ブランド「インフィーア」は、独自性があり性能が高いと好評。 趣味は、ツーリングで自然を見に行くのと、筋トレ、読書。 |
|
|
|
|
その他の、不動産相続関連の記事は以下もぜひご覧ください。
不動産相続税金対策とは?
https://regavel-auction.com/info/609/
不動産相続相談先はどこ?不動産相続を相談する時の注意点も紹介
https://regavel-auction.com/info/611/
不動産相続登記に必要な書類は?
https://regavel-auction.com/info/614/
不動産相続の名義変更必要書類とは?
https://regavel-auction.com/info/615/
不動産相続とは?
不動産を相続する場合、「相続登記」をする必要があります。
相続登記は、故人名義の不動産登記簿を相続人の名義に変更する手続きで、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した場合、知った日または遺産分割協議成立日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となりますので、慎重に手続きを進める必要があります。
相続した不動産の売却手順
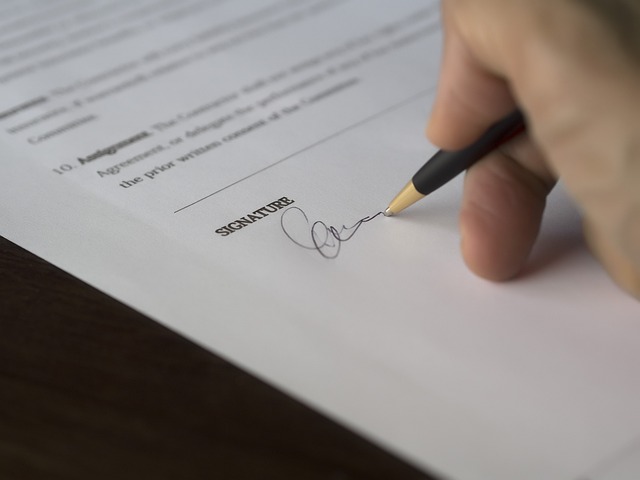
相続する財産や相続人を確認する
被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を提出します。
葬儀や世帯主の変更届、金融機関への連絡、公共料金の解約・名義変更などさまざまな手続きと平行して、相続の手続きと協議も進めなければなりません。
平等な相続は全ての相続人が納得するのが難しく、親族間のトラブルを引き起こす可能性があるため、まずは遺言書の確認、相続人の調査、遺産の確定などを確実に進めることが大切です。
専門家に相談するのもおすすめの選択肢です。
遺言書有無の確認
相続においては、「被相続人」は故人の事で遺言書の有無により手続きが大きく変わります。
まずは遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言の有無を事前に確認できると良いですが、通常は自宅の引き出しやタンス、金庫、貸金庫などに保存されている可能性があります。
公正証書遺言がある場合は、公正証書遺言検索システムを利用して探すことができます。
遺言が見つかった場合は慎重に取り扱う必要があります。
遺言書の偽造や複製を防ぐためには、家庭裁判所で「検認」手続きが必要であり、遺言書は勝手に開封してはいけません。
法定相続人の調査・確定
遺言書が見つかった場合は、その内容に基づいて相続手続きを進めてください。
遺言書がない場合は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を入手し、出生から死亡までの情報を確認して相続人を特定します。
親、兄弟姉妹、子、認知した子、養子などの親族関係を洗い出し、相続人を確定させます。
法務局では、亡くなった方の戸籍や相続人の住民票を提出して「相続情報一覧図」にして証明する制度もあります。
被相続人の配偶者は法定相続人であり、次いで子供、父母、兄弟姉妹の順序が決まっています。
相続財産の調査・確定
法定相続人が確定したら、次に相続財産を調査します。
本記事では、主に不動産の相続手続きに焦点を当てていますが、相続財産には不動産以外のものも含まれ、総合的な判断が必要です。
通常、大きな資産とされるのは預貯金と不動産です。
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も考慮されます。
自宅、勤務先、取引先などからどのような財産があるかを調査しましょう。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産と葬儀費用を差し引いた金額に対して発生します。
⚫︎相続財産の例
プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券(株式など)、ゴルフ会員権、宝石、貴金属など
マイナスの財産: 住宅ローン、カードローンなどの借金、未払いの税金など
相続放棄を考える場合は、相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てができます。
多くの必要書類が必要であり、早めの対応が必要です。
相続放棄をすると、相続権利が後位の法定相続人に移り、責任の放棄となりかねない点に注意してください。
必要書類の準備

相続手続きには非常に多くの書類が必要です。
書類の準備には遠方からの郵送なども含まれ、時間がかかることが予想されますので、早い段階で手配を始めることが重要です。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票の除票(本籍記載のあるもの)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日付以降のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員分の住民票の写し
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・対象不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書
上記の書類を集める際には、特に相続人全員の協力が必要であり、手続きを円滑に進めるためにも早めの対応をしましょう。
遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に進みます。
遺産分割協議は、相続人同士が行う遺産の分割に関する協議会議です。
この協議において、後に述べる「遺産分割協議書」に相続人全員の署名捺印があれば、直接会って協議する必要はありません。
遺産分割協議書の作成
協議が無事に終わり、分割内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。
形式や書式に厳格なルールはありませんが、土地や建物などは登記簿謄本に基づいて正確に記載してください。
この書類には、相続人全員が署名捺印する必要があります。
遺産分割協議における注意点
遺産分割協議は裁判外での話し合いの場であり、法的な制約はありません。
期日も設けられておらず、納得が得られるまでゆっくり話し合いを進めることができます。
一方で、法的な制約がないため、強制力が働かない可能性があります。
遺産分割協議が進まない場合、最終的には相続人全員の署名捺印が必要ですが、どうしても進まない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
相続登記の申請の流れと費用

相続登記の申請の流れ
・相続する不動産の登記事項証明書を取得
・遺産分割協議書の作成
・相続登記申請書の作成
・相続登記申請(法務局で手続き、もしくは郵送)
費用
・必要書類取得費用
登記事項証明書や住民票などの取得にかかる費用は1,000〜10,000円程度(必要書類の数による)
・司法書士報酬
司法書士に依頼する場合、報酬は数万円から10万円程度。
必要書類や不動産の数によって金額が変動します。
費用は必要な書類や手続きの複雑さによって変動します。
司法書士に相談して具体的な見積もりを取ることが重要です。
相続税の申請して納付
相続の発生から10カ月以内に相続税の申請及び納付が行われます。
申告期限を過ぎたり、納税額が不足していたりすると、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
相続税には基礎控除額があり、この控除を差し引いた残額に対して相続税が課せられます。
遺産総額が基礎控除額よりも少なければ申告の必要はありません。
不動産の相続時に発生する税金

相続において気になるのは相続税やその他の費用です。
被相続人から相続人へと贈られる形で生じるのが「相続税」です。
相続税は、控除や特例を利用することで軽減することができる場合もあるため、基礎知識として把握しておくことが重要です。
不動産の相続税評価額
・土地の評価額
路線価方式
周辺の土地価格や地域の特性を基に評価されます。
倍率方式
地域ごとに設定された倍率を基に土地面積で評価されます。
土地の相続税評価額はこれらの方式により求められます。
通常、売却価格よりも低い評価額が適用されるため、多額の課税の心配は少ないです。
・建物の評価額
自宅や建物の部分は固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」が使用されます。
評価額は相続税の計算に用いられ、具体的な価格の評価には地域や特性に基づいた査定を専門家に頼むこともおすすめです。
相続税の計算方法

相続税の計算は不動産だけでなく、相続遺産全体が対象です。
預貯金や有価証券などのプラスの財産も考慮され、総額が基礎控除額を超えると相続税が発生します。
基礎控除額は相続人の数によって変動し、相続税改正に伴い注意が必要です。
・基礎控除額の計算
基礎控除額 = 3,000万円 + 相続人の数 × 600万円
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名いる場合、基礎控除額は4800万円となります。
遺産総額がこの額を超える場合は相続税が発生します。
遺産総額を相続人ごとに分割し、相続税率を掛けて納税額を計算することで実際の負担額がわかります。
その他の控除や特例
相続税の引き下げには、基礎控除額を超えても控除や評価額減額の特例を活用することがあります。
配偶者控除
配偶者は、最大1億6,000万円または法定相続分のうち多い方まで相続税がかかりません。
これを最大限利用する場合、二次相続時の子の相続税負担が増える可能性があるため、二次相続対策も考慮する必要があります。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地や貸付事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額する特例です。
一定の条件を満たしている必要がありますが、大きな評価額減額の特例となります。
これらの控除や特例を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
相続不動産におけるトラブルを回避するための遺産分割方法

・現物分割
不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法。
・代償分割
不動産を1人が取得し、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法。
・共有
不動産を相続人で共有する方法。
・換価分割
不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法。
現金化が難しい不動産の遺産分割は、これらの方法を検討することが一般的です。適切な分割方法は、相続人の合意や不動産の性質により異なります。
売却を前提に考えるなら換価分割
実際には、わずかな遺産でも相続が発生し、その分割に関する問題が起こることがあります。
特に資産が少なくても、増税や経済の不安が影響し、相続を期待するケースも増えています。
資産が少なくても、同居や移住などの計画がある場合は、現物分割、代償分割を検討すると良いでしょう。
一方で、誰も住む予定がない場合や相続人が複数いる場合は、換価分割がトラブル防止に役立つ方法です。
換価分割では、相続人が売却して得られた代金を分け合います。
この際、遺産分割協議によって売却担当者や分配のルールを決め、トラブルを未然に防ぐことができます。
相続した不動産は放置しておくと損をする可能性が高い
相続によって親から不動産を受け継ぐ場合、税金が発生し、管理が難しい場合は売却を検討することがあります。
放置すると固定資産税の支払いが続きます。
⚫︎売却のメリット
・固定資産税の軽減や維持管理の手間を軽減できます。
・現金化により相続税の支払いに充てたり、他の運用に利用できます。
⚫︎手続きと注意点
・不動産の評価額や売却代金によっては相続税がかかることがあります。
・不動産の売却手続きは、専門家や不動産業者の協力が重要です。
⚫︎相続税の課税対象
相続税の基礎控除を超える金額が相続遺産に含まれます。
⚫︎不動産の査定
専門の不動産査定業者や不動産仲介業者に依頼して、適切な評価を受けることが重要です。
⚫︎売却先の選定
不動産仲介業者やオンラインの不動産プラットフォームを通じて売却先を選定します。
不動産の売却には検討と専門家の協力が必要です。
相続した不動産の売却にも相続登記が必要

相続登記の義務化により、相続した不動産を売却する際は相続登記が必要です。2024年4月からは登記を怠ると10万円の過料が発生する可能性があります。
相続登記は、名義を変更するだけでなく、以下のようなデメリットを回避するためにも重要です。
・売却のスムーズ化
相続登記が完了していれば、不動産の売却手続きが迅速かつ円滑に進行します。
・所有権の明確化
相続登記により、不動産の所有権が明確になり、購入希望者にとっても安心材料となります。
・法的トラブルの防止
登記がないままの状態では、法的トラブルや争いの原因になる可能性があります。相続登記はそのリスクを軽減します。
・過料の回避
義務化に伴い、相続登記を怠ることで発生する10万円の過料を回避するためにも、正確かつ迅速な登記手続きが必要です。
自分で相続登記を行うことも可能ですが、専門家の助言を得るか、司法書士に依頼することが一般的です。
相続登記を行わないことで発生するリスク

以下のリスクを軽減するために相続登記が重要です。
相続登記を行うことで、以下のようなメリットがあります。
・処分の自由化
相続登記を完了することで、相続人が所有権を持ち、自由に不動産を処分できるようになります。
他の相続人が単独での登記が難しくなり、合意が必要な状態になります。
・売却の防止
相続人が一方的に売却することが困難になります。
合意を得ない限り、不動産の売却は難しくなります。
・賠償の可能性
不測の事故や損害発生時に、相続登記を行っていれば、不動産賠償の権利を行使することができる可能性があります。
・相続人の増加
相続登記が行われていれば、将来的な相続人の増加にも柔軟に対応できます。
相続人が変わっても、正確な所有権情報が登記に残ります。
上記の点を考慮し、相続不動産に関する手続きや登記が大切です。
相続した不動産であっても譲渡益の申告が必要
相続した不動産の売却には、取得費や減価償却費の情報を把握することが重要ですが、売買契約書が見つからない場合でも、5%相当額を取得費として利用できます。
税務に関する詳細な情報は税理士や専門家と相談することがおすすめです。
相続税を支払った場合、譲渡税を軽減できる
相続税申告期限から3年以内(相続から3年10ヶ月以内)に相続不動産を売却する場合の「相続税の取得費加算の特例」は、税金の軽減に関係がある重要な措置です。
これを活用することで、相続により取得した不動産を売却した時の譲渡所得から支払った相続税を費用として計上できることができ、譲渡所得税の節約をすることができます。
具体的なケースによっては複雑な要素が絡むため、税理士や専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
相続した不動産を売却する際の注意点
税金特例や取得費に関する事項は、正確な情報を把握しておくことが重要です。
相続税の特例や相続税の取得費加算の特例を上手に利用することで、税金の軽減が期待できます。
取得費が不明な場合は、代替資料を見つけることも大切です。
相続不動産の売却においては、専門家のアドバイスを受けることも検討してください。
スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探す
不動産の売却は様々な要因が影響を与えるため、スムーズで高額な取引を実現するためには、信頼性のある不動産会社の選定が鍵となります。
専門性や実績、相続に特化したサービスなどを比較検討し、適切な不動産会社に相談することが大切です。
相続税や特例の期限も意識して、計画的な売却手続きを進めることが望ましいでしょう。
共有名義の売却は全員の同意が必要となる
共有名義の不動産を売却する場合は同意が必要で、価格の合意も重要なポイントです。
特に価格の同意は複数の共有者が合意することが求められますが、最低売却価格の設定がスムーズな意思決定を促進し、スムーズな売却につながります。
共有者同士のコミュニケーションと協力が重要です。
単独登記型は贈与にならないようにする
単独登記型での売却は確かに柔軟性がありますが、贈与にならないよう十分な配慮が必要です。
特に、遺産分割協議書に換価分割目的を記載することで、将来の問題を防げるというのは重要なポイントです。
透明かつ円滑なコミュニケーションが、相続人間の理解を深めるのに役立つでしょう。
親の家に住む場合と住まない場合では税金特例が異なる
「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」は、相続税において特定の条件を満たす場合に利用できる重要な特例です。
これらを活用する際は、国税庁の公式情報に従いながら、確定申告時に必要な資料を準備することが大切です。
また、「居住用財産の特例」において、住んだ期間や目的による条件があることを理解し、特例の利用が認められるケースかどうか検討する必要があります。
確定申告時に提出が必要な資料にも注意して、手続きをスムーズに進めることが重要です。
取得費は親の購入額を引き継ぐ
相続した不動産を売却する場合、取得費の計算が重要です。
親が不動産を購入した際の売買契約書を見つけ、土地と建物それぞれに対する購入額を確認し、減価償却費を考慮して正確な取得費を算出することが必要です。
この取得費は、譲渡所得の計算において重要な要素となります。
相続不動産売却に関するよくある質問
いつまでに不動産の名義変更をしたら良い?
不動産の名義変更手続きには特定の期限はありませんが、相続後早めに手続きを行うことが重要です。
放置すると相続トラブルの原因となり得ます。
特に2024年から相続登記が義務化されたことを考慮すると、相続者は相続により不動産の所有権を取得したことを知った日または遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記を申請する必要があります。
この期限内に手続きを済ませることで、過料の対象から免れ、スムーズな相続手続きが期待できます。
まとめ
今回は、相続不動産売却手順などについて詳しく紹介しました。
相続不動産売却手順について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
紹介した内容を参考にして相続不動産売却手順に関する知識を深めて下さい。
その他の、不動産相続関連の記事は以下もぜひご覧ください。
不動産相続税金対策とは?
https://regavel-auction.com/info/609/
不動産相続相談先はどこ?不動産相続を相談する時の注意点も紹介
https://regavel-auction.com/info/611/
不動産相続登記に必要な書類は?
https://regavel-auction.com/info/614/
不動産相続の名義変更必要書類とは?
https://regavel-auction.com/info/615/
この記事の関連記事

2025年現在の東京の不動産市況:売り時はいつか?
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…

[再建築不可] 接道義務と43条但し書きとは
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…

[不動産査定] 不動産の路線価とは何なのか?計算方法をご紹介
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…

埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良い?
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…

横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社は?
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…

不動産売却の費用を詳しく解説
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…

不動産売買契約書とは?
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…

不動産相続手続きとは?
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…